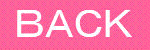エレブ大陸に巻き起こった戦いの最中、若きフェレ侯爵エリウッド率いる軍勢の中では、長い旅と戦いを経て幾人かの男女が心を通わせていた。
エリウッドと踊り子ニニアン、サカ草原の遊牧民族ロルカ族のリンとクトラ族のラス、
そしてオスティア侯爵の弟ヘクトルと、イリア出身のフロリーナもその中の一部であった。
ところが順調に進んでいるエリウッドやリンたちに比べ、
ヘクトルとフロリーナの関係は、互いの信頼関係こそあるものの、それ以上にはなかなか進まない状況が続いていた。
それはフロリーナが極度の男性恐怖症である事と、ヘクトルが重騎士並みの立派な身長と体格の持ち主であることも原因であった。
フロリーナはヘクトルに心を開いてはいたが、元々の気の弱さと身に染み付いた男性への反応は、簡単に消える事は無かったのである。
ある晴れた日、ヘクトルは軍勢の宿営地から少し離れた湖で、ペガサスに水浴びをさせているフロリーナを見つけた。
彼女は肩当てと胸当てを外し、ブーツを脱いで湖の浅瀬に入っている。元から軽装なペガサスナイトではあるが、
わずかな防具を外してしまうと完全に騎士の面影はなく、年頃の可憐な娘にしか見えなかった。
ヘクトルは口元に指を当てて「へえ」と感心した様子で呟くと、ペガサスの世話に夢中なフロリーナに近付いた。
「よう、やってるか」
「ひゃあっ!?」
背中越しに声を掛けた途端、フロリーナはヘクトルの大きな身体を見て悲鳴を上げ、湖底の石につまずいて後ろに尻餅をついてしまった。
フロリーナはびしょ濡れになりながら、潤んだ瞳で目の前に立つヘクトルを見上げる。ウェーブのかかったふわふわの髪も、水に濡れてすっかりしぼんでしまっている。
ヘクトルは「あちゃー」と左手で目元を押さえ、水の中に座り込んだままのフロリーナに手を差し伸べて言った
「悪い、驚かすつもりはなかったんだけどな。大丈夫か?」
「あ、その、あの……は、はい、大丈夫です……」
フロリーナがおそるおそる伸ばした手を掴み、ヘクトルは彼女を引き上げる。
彼にとってはごく普通の振る舞いであったが、フロリーナはヘクトルと肌が触れただけで、はっきりと聞こえるほど胸の鼓動が高鳴ってしまっていた。
うつむいて顔を赤らめるフロリーナに、ヘクトルは後頭部を掻きながら小さくため息をつく。
「男が苦手ってのは聞いてるが、ちょっと重症だなこりゃ」
「す、すみません」
「まさかと思うが、俺の顔を忘れた訳じゃないよなあ?」
「そんなことはありませんっ!」
と、珍しくはっきり返ってくる返事にヘクトルは一安心し、口の端を少し持ち上げて笑う。
「とにかく悪かったな。そのまんまじゃ風邪引いちまうだろうし、毛布と着替え持ってきてやるよ。ここで待ってな」
「あ……」
ヘクトルは踵を返し、キャンプのある方向へと走っていく。フロリーナは言葉を途切れさせたまま、じっとヘクトルの後ろ姿を目で追っていた。
そんな出来事があってから約一時間後。
「ちょっとヘクトル、あなたフロリーナになにをしたの!」
と、キャンプで鎧の手入れをしているヘクトルに、眉をつり上げて迫るのはフロリーナの親友リンである。
気弱なフロリーナと違い、彼女はヘクトルを恐れたりせず、言葉にもまったく遠慮がない。
気丈で快活な性格ながらも、貴族の血を引いていることもあり、人を惹き付ける美しさを備えた顔立ちであり、サカの青い衣装に身を包み、長い髪を後ろで束ねている。
「なにって、別になんもしてねえよ」
「じゃあどうして湖でびしょ濡れになって落ち込んでるわけ?」
「いや、それはだな……」
「いいヘクトル。もし彼女を泣かせるような真似したら、私が許さないわよ」
「だから違う……って、おいこら話を聞け!」
言いたいことだけを矢継ぎ早に言い放つと、リンはヘクトルに背を向けてさっさと離れていってしまう。
本当ならもう二言三言付け足したいところだが、フロリーナの手前それは我慢していた。
リンが自分のテントに戻ると、中には着替えを済ませたフロリーナと、少し前に声を掛けて呼んでおいたニニアンが座っている。
リンは二人の前に腰を下ろすと、それぞれの顔を見てから話し始めた。
「みんな待たせちゃってごめんね。実はさっき、ヘクトルのせいでフロリーナが湖でびしょ濡れになっちゃって。まったくがさつなんだから」
「違うわリン。あれはドジな私が悪いの。だから……ヘクトルさまを悪く言わないで」
肩を落として小さくなっているフロリーナにこれ以上も言えず、リンは口を閉じる。
「あの、今日はどんな相談なのでしょう?」
そう訊ねたのは、穏やかな雰囲気と、腰まで届く美しい髪が特徴のニニアンである。
リンは自分自身が、ニニアンとフロリーナはそれぞれ好きな相手が軍勢の中心人物という事もあって顔を合わせる機会が多くなり、
自然と三人は集まって話し合うことが多くなっていた。
「そうそう。今回集まったのは、フロリーナとヘクトルについてなんだけど」
「ええっ。ちょっとリンってば」
動揺するフロリーナに笑いかけながら、リンは続ける。
「二人ともいい感じにはなってるみたいなんだけど、なんていうか……エリウッドとニニアンみたいな、いかにも恋人ですって感じじゃないのよねー」
「もう、リンさまったら……」
「それでニニアンに聞きたいんだけど、二人の関係が進展しない原因ってなんだと思う?」
「急に言われましても……難しいですね。フロリーナさんは男性が苦手なのですし」
「そう、そうなのよね。それをフロリーナは精一杯頑張って気持ち伝えたんだし、彼女は悪くないと思うの」
「それじゃあ問題はヘクトルさまにあると?」
「そうとしか考えられないわ」
「でも、エリウッドさまはヘクトルさまのこと、いつも世界で一番信用できる友人だと……」
「私だって信用はしてるけど、それとこれとは別よ。男女の事ではやっぱりがさつだもん。だからちょっと考えたんだけど」
リンはニニアンからフロリーナに視線を移し、訊ねた。
「ねえフロリーナ、ちょっと付き合ってもらっていい? ニニアンも一緒に行きましょう」
三人は連れ立ってテントを後にし、エリウッドがいる宿営地の本陣へと足を向けた。
リンたちが訪れたときには作戦会議なども一段落し、エリウッドも自由になったところであった。
エリウッドはすらりとした体格の、優しげな面影のある若者で、
礼儀作法や立ち居振る舞い、言葉遣いに至るまで、フェレ侯爵の後継者として十分な資質を身に付けていた。
リンはエリウッドが一人でいるのを見計らい、フロリーナに一人で話しかけるよう言って背中を押した。
フロリーナは戸惑いながらもエリウッドに近付き、小さくお辞儀をして話しかけた。
「あの……こんにちは」
「やあフロリーナ、こんにちは。今日はリンたちと一緒じゃないのかい?」
「い、いえ、その……」
「そうそう、近頃はニニアンとも仲良くしてくれてるそうだね」
「はい、ニニアンさんはとっても優しくて、お話ししやすいんです。生まれ故郷も私と同じイリア地方だと聞きました」
「そうか。彼女はあまり他人と関わりたがらないから、フロリーナのような友達ができてきっと喜んでいるさ」
「そうだと私も嬉しいです」
「ニニアンが楽しそうにしていると、僕も嬉しくなる。ありがとうフロリーナ」
「そんな……恐縮です」
「それじゃあ僕は次の用事があるから、そろそろ行かなくては。ヘクトルに会ったら、明日の稽古に付き合ってくれと伝えておいてくれないかな」
「あ、はい、わかりました」
エリウッドは優しく微笑むと、颯爽とその場を後にした。
フロリーナが戻ってくると、様子を見ていたリンは納得したような顔で頷き、彼女の手を引いて今度は宿営地の外れにやってきた。
そこには膝を曲げて座る白馬の傍らで、弓の弦を調整しているラスがいた。
ラスはサカの民クトラ族の出身で、幼い頃から各地を放浪し、傭兵として戦場を生き抜いてきた寡黙な男であった。
必要以外の言葉を口にせず、鋭い眼差しと実直な顔立ちは、近付きがたい無言の迫力があった。
リンはエリウッドの時と同じように、フロリーナの背中を押して彼に話しかけるようにと促す。
リンの考えていることを不思議に思いつつ、フロリーナは恐る恐るラスに声を掛けた。
「あ、あの、こんにちは」
「……」
「あれ?」
「……」
「こんにちは」
「……」
何度呼びかけても、ラスからの返事は無い。少し不安になりながら、フロリーナはもう一度呼びかけた。
「えっと……あの、聞こえてますか?」
「なんの用だ」
「ひゃっ!?」
突然口を開いたラスに驚き、フロリーナは裏返った声を出してしまう。
「えっと、その、特に用事はないんですけど……」
「そうか」
それっきり、ラスは再び口を閉じてしまう。
沈黙に困って背後を振り返るが、離れたところから隠れて見ているリンは「もう少し頑張って」とジェスチャーを返してくる。
仕方なくフロリーナは、頭の中であれこれと考えた挙げ句、ラスに訊ねてみることにした。
「あ、あのラスさんは恐いものとかあるんですか?」
「……」
「私、すごく恐がりだからいつも思うんです。戦いが始まったときとか、みんなは恐くないのかなって」
「恐いに決まっている」
「ひゃっ、また急に……」
「だが恐怖で縮こまっていたら、多くのものを失う事になる。仲間も、自分の命もな。だから立ち向かうしかない。お前もそうやってここまで来たのだろう?」
「は、はい」
「相手をよく見ろ。そうすれば恐怖は克服できる。俺が言えるのはそれだけだ」
「相手を……」
「それからリンにも、隠れるならもっと上手くやれと伝えておくんだな」
「ええっ、どうして分かったんですか?」
「風上に隠れる奴があるか。風に匂いが乗っている」
「す、凄い」
「さあ、もう行け。これ以上話せることはない」
「あの、ありがとうございました」
ラスの考え方や鋭さに驚きながらも、会話の中でなにか大事なヒントを得たような気分になりながら、フロリーナはリンとニニアンの元へ引き返す。
合流した三人は再びテントに戻り、最初と同じように顔を向かい合わせて座る。
「さて、今回の事で分かったんだけど」
と、口を開くのはやはりリンである。
「やっぱり問題はヘクトルにあると思うのよね」
「なぜそう思ったんですか?」
ニニアンが聞き返すと、リンは人差し指を立てて言う。
「思い出してみて。エリウッドやラスとは、フロリーナも普通に喋ることができたわよね。
二人とも急に大声出したり、急に乱暴な事したりしない雰囲気があるじゃない。つまりヘクトルには紳士的な部分が足りないのよ」
「そ、そういう問題なのでしょうか?」
「じゃあニニアンは、もしもエリウッドがヘクトルみたいな性格だったら好きになってた?」
「そ、それは……でもエリウッドさまはエリウッドさまだし……」
考え込むニニアンの横で、フロリーナも苦笑している。
「あのねリン、私のことでそんな騒がなくても大丈夫だから」
「ううん、ヘクトルはもう少し女の子に気を遣うべきよ。とにかく私に任せておいて」
心配するフロリーナをよそに、リンは考えていた計画を実行に移す準備を始め、そして夜が明けた。
「……おい、なんだこれは」
と、不機嫌そうな声を出したのはヘクトルである。エリウッドとの稽古が終わった後、彼に誘われてやってきた小屋の中には、
小さな机と黒板があり、黒板には大きな文字で「貴族の紳士マナー講座」「一日わずか五分だけ」「これで君も紳士になれる」などといった文字が書き込まれており、
ヘクトルは唖然して口を開けたままエリウッドを見た。
「見ての通りさ。ちょっと頼まれて、君に紳士的な振る舞いを身に付けさせるように言われてね」
「こりゃあ誰の差し金だ? さしずめオズインか……いやいや、こんなくだらねえ事を思いつくのはマシューの野郎か、あるいはセーラとか」
「残念ながら全部ハズレだ。とりあえず席に座ってくれヘクトル」
「おいおい、俺がこんなもん勉強してお上品になると本気で思ってるんじゃないだろうな」
「はは、君の性格はよく知っているよ。だが僕も頼まれた手前、義務は果たさないといけないからね」
「ちっ、誰だこんな面倒くせえ事を考えた奴は。見つけたら痛い目に遭わせてやるぞ」
「まあ落ち着いてヘクトル。これは君と、それからフロリーナのためでもあるんだよ」
「……なに?」
「つまりそういうことさ。じゃ、始めようか」
「ったく、仕方ねえな。お前の顔を立てて付き合ってやるよ」
ヘクトルは鎧を身につけたまま椅子に腰掛け、エリウッドの出す問題にひとつずつ答え始める。そしてあっという間に一時間ほどが過ぎた。
「……凄いな、完璧じゃないか」
エリウッドは笑顔を浮かべながら、質問全てに答えきったヘクトルに拍手を送る。
「当たり前だっつーの。こんなもんガキの頃からさんざん叩き込まれてんだ。エリウッドだって知ってるだろうが」
「まあね。君は型破りな性格だが、礼儀作法は僕以上にしっかり身に付けていた。貴族同士の集まりでそれを知ったとき、大したものだと感心したよ」
「義理は果たすが、俺は堅苦しいのと息苦しいのが嫌いなんだよ。ま、これでお前の義務とやらは果たせただろ。これ以上はアホらしくて付き合ってらんねーぞ」
ヘクトルは席を立ち、凝った肩を揉みながら小屋の外へと出て行った。
その姿を見送ったエリウッドが黒板の文字を消していると、リンとニニアンがひょっこりと姿を現した。
「ねえねえ、どうだった? 少しは変化ありそう?」
興味津々に訊ねてくるリンに、エリウッドは苦笑いを浮かべながら首を振る。
「ええーっ、どうして?」
「ヘクトルは元々、礼儀作法は完璧なんだよ。それでもああいう風に振る舞うのは、元々の性格がああだからさ。
それを無理矢理変えようとしてしまうのは、僕はあまり感心しないな」
「でも、それじゃフロリーナが……」
困った様子で肩を落とすリンを元気付けるように、ニニアンが彼女の肩にそっと手を置いて微笑みかける。
「大丈夫ですよ。ヘクトルさんもフロリーナさんもお互いに通じ合っているんですから、少しずつ心を通い合わせていけば、自然と上手く行くはずです」
「だといいんだけど、やっぱり心配なのよね」
「エリウッドさまは、素性の知れない私をそばに置いてくれて……本当のことを打ち明けられないと言った時も、それでも構わないとおっしゃってくれました。
だからご友人のヘクトルさまも、エリウッドさまに負けないくらい立派で素敵な方だと私は思います」
「それは……わかってるけどさ」
ヘクトルが仁義に厚い人物であることはリンにも分かっていたが、
豪快な彼の性格と、男嫌いで気弱なフロリーナの性格が上手く噛み合う場面をどうしても想像できなかった。
しばらく考えてからヘクトルを追い掛けようと決めたリンが振り返ると、
いつのまにかエリウッドとニニアンが身を寄せ合い、二人だけの世界に突入して声を掛けられるような状態ではなくなっていた。
「んもう、ごちそうさま」
リンは聞こえないように呟くと、音を立てないように小屋の戸を閉め、ヘクトルが歩いて行った方向に駆け出していった。
フロリーナは愛馬のヒューイを連れて草原に行き、ヒューイが草を食べている様子を、十メートルほど離れた場所にある石に腰掛けて眺めていた。
時折吹き抜ける風が、彼女の髪を柔らかになびかせる。
頬を撫でる毛先を指で掻き上げながら、静かな時を過ごす事は、争い事を好まないフロリーナにとって、心の平安を保つ大切な時間であった。
ふと、背後から草を踏む音が聞こえて振り返ると、太陽の日差しを背にした大きな男がゆっくりと近付いて来るのが見えた。
思わず声を出しそうになったが、その相手が誰だか分かると、フロリーナはほっとした気持ちで心を落ち着かせた。
「よう、今日は驚いてひっくり返らないのか」
明るい口調でそう言ったのは、鎧を外して普段着の姿となったヘクトルであった。
普段から鎧を着込んだまま平然と歩き回り、戦いでも先陣を切って戦う彼のこうした姿が見られるのは、この旅の間では珍しい事だった。
ヘクトルは鎧を脱いでも見劣りのしない、立派な体格の持ち主で、短めの髪を全て後頭部側に流し、顔立ちも男らしい精気に満ちている。
「も、もうそんな事にはなりません」
「はは、だといいけどな」
「どうしてここが分かったんですか? 今日は誰にも言ってなかったのに」
「それはな」
と、ヘクトルは自分の鼻を指してニッと笑い、
「こう見えても俺は鼻がきくんだよ。ここは風が吹いてるだろ。その風に乗って、お前の匂いがしたんだ」
「ええっ」
知らないうちに変な匂いを出していたのではと彼女は焦ったが、ヘクトルはそんな不安を打ち消すように笑い、フロリーナの頭を軽く撫でて言った。
「心配すんな。お前の髪のいい匂いさ。ちょっと甘い花の香りみたいな」
「そうですか、よかったあ」
安堵に胸をなで下ろすフロリーナは、ごく自然に笑った。その表情を見て、ヘクトルも口の端を持ち上げて頷く。
「なんだ、ちゃんといい顔で笑えるんじゃねえか」
「えっ」
「お前、いつも緊張してたろ。俺といる時以外でも、男と喋ってる時は大体そうだったな」
「は、はい。なんとかしなきゃっていつも思ってるのに、気付いたら身体が固まって……」
「なあ、そもそもお前が男嫌いになった理由ってなんなんだ?」
「えっ、理由ですか?」
「わけもなく突然恐くなったりはしねえだろ。そういうのは必ず原因があるはずだ。心当たりがないか思い出してみろよ」
「えっと……」
フロリーナは言われて初めて、自分の男性恐怖症がいつから始まったのか記憶を遡ってみた。
するとそれは、まだ彼女が幼い頃、故郷であるイリアの村で暮らしていた時の出来事が発端である事に気がついたのである。
「あ……思い出しました」
「本当か。ちょっと聞かせてみろ」
「はい。ご存じの通り、イリアはとても寒い土地で、みんな傭兵としていろんな人に雇われて暮らしているんですけど……
私がまだ小さかった頃、私の住んでいる村に、天馬騎士を雇いたいという男の人たちが来た事があるんです。
だけど話し合いがまとまらなくて、私のお母さんとその相手が言い争いになりました。
その時の男の人たちがすごく乱暴で、部屋の物を壊したり汚い言葉を口にしてて……
結局その人たちはすぐに帰ったんですけど、それからしばらくの間、私は眠れない日が続きました……それからです、男の人が恐くなったのは」
話し終えた頃には、フロリーナは両目にうっすらと涙を浮かべていた。幼心に刻まれた心の傷は、今も癒えることなく彼女の心に残り続けていたのである。
「なるほどな。もし俺がその場にいたら、その馬鹿野郎どもをひねり潰してるところだ」
「ありがとうございます。だけどもうずっと昔の事なのに……未だに引きずってるなんて」
「仕方がねえさ。戦場に出てくる男なんて大抵はロクでもない連中ばかりだからな。平和な時はまともだった奴が殺人鬼にもなる……それが戦争ってもんだ」
「はい……」
「けど確かに、いつまでも恐い恐いとも言ってらんねえよな」
「でも私、どうしたらいいのか分からなくて。頑張ろうとはいつも思うんですけど」
「そうだな。まずは目の前にいる相手をよく見な」
言われてフロリーナは、自分の目の前に立つ若者の顔を見上げた。大きな体格に太い腕、分厚い胸元。
自分とはまるで違う体つきの「男」がそこにいると認識すると、知らず緊張して身体が強張ってしまう。
その感覚から逃れるために目を逸らそうとすると、ヘクトルがすかさず「目を逸らすな」と告げた。
「相手の事が分からなきゃ恐いのは当然だ。俺も図体はでかいが、お前を恐がらせた連中と同じか?」
フロリーナは首を左右に振って返事をする。
「エリウッドにしてもそうだろ。あいつが乱暴な奴らと違うって分かるから、普通に喋る事もできるんだ。後は慣れさ」
「でも、私にできるのかな……」
「出来るに決まってんだろ。ペガサスってのは背中に乗るまですげえ苦労するって聞いたぜ。
お前にはそれが出来たんだから、男が苦手なのも少しずつ直していけばいいんだ」
「は、はいっ!」
「ただし戦場で無理はすんなよ。ヤバい時は俺が守ってやるから。大事なお前に指一本触れさせやしねえよ」
「はい、あの……ありがとうございます。私、私……」
相手をよく見ろという言葉は、ラスも同じように口にしていた。フロリーナはその事を思い出し、じっとヘクトルを見る。
大きな身体とがさつな口調の中に、ヘクトルの細やかな気遣いが隠れている事を知ったフロリーナは、瞳に映る彼の姿に、太陽のような暖かさを感じていた。
だから、今こそ精一杯の勇気を出そうと決めた。
「あ、あの……ヘクトルさま」
「ん、どうした?」
フロリーナは立ち上がってみたが、ヘクトルは背が高くて少しばかり距離が足りない。そこで腰掛けていた石の上に乗り、彼の首元に抱きついた。
「お、おい」
「だ……い……好き……です……」
ほとんど聞き取れないような小さな声だったが、それが今の精一杯だった。
風の音にかき消されてよく聞こえなかったが、ヘクトルにもフロリーナの気持ちは温もりと共に伝わっていた。
彼女の背中に手を回してポンポンと優しく叩いてやると、力が抜けたのか、フロリーナは石から足を滑らせてしまい、彼女の体重が一気にのしかかってきた。
さすがのヘクトルもこれには不意を突かれ、フロリーナを抱きかかえたまま草の上に倒れ込んでしまう。
クッションのような草の上で互いの顔を見合わせた後、ヘクトルとフロリーナは笑い合う。
その声に惹かれてか、ペガサスのヒューイも側に近寄って二人の様子を見守っていた。
ヘクトルとフロリーナの笑い声が聞こえたのと同じ時、その場所が見える丘の上にラスの駆る白馬が現れ、走り抜けざまに草の中からなにかを拾い上げた。
それはヘクトルとフロリーナの様子を、地面に伏してじっと覗いていたリンであった。
「ちょ、ちょっとなにするのよ。驚いたじゃない」
ラスの腕から馬の背によじ登りながら、リンが少しむくれた顔をする。
「あまりいい趣味とは言えんな」
「だって……心配だったのよ」
「フロリーナも子供じゃない。友人なら分かっているだろう」
「……ねえラス。私のしようとした事って、ただのおせっかいだったのかな」
「そうだな」
「うっ。はっきり言われちゃうと結構ショックね」
「だが俺たちは戦争の真っ只中にいる。誰もが明日も知れない身だ。そんな中で仲間や友人のために親身になれる人間を、悪く言える奴はいない」
「うん……そうだと嬉しいな。ありがとうラス」
二人を乗せた馬は、風が吹き抜ける草原を駆け抜けていく。
エリウッド、ヘクトル、そしてリンの三人が平和を勝ち取り、愛する者との平和な日々を過ごすのは、これからもう少し先の事である――。
ちくわぶさんから誕生日祝いに小説をいただいちゃいましたーvv図々しくもリクエストしたFE烈火のヘクフロ、エリニニ、ラスリンです><
まさか…3組とも話に入れてもらえるなんて思ってなかったんで本当に嬉しいです(;ω;)ひたすらにやけっぱなしでした、萌えをごちそう様です←
ヘクフロの可愛さが特にたまらないです////身長差とか、男性恐怖症乗り越えるとか、おいしい要素がいっぱいです(´`*)
ちくわぶさん、素敵な小説ありがとうございます!